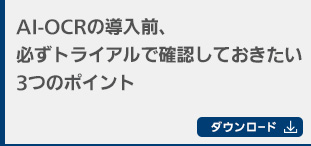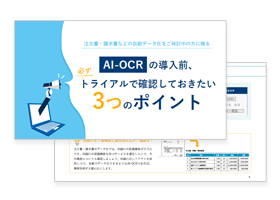電子帳簿保存法における電子保存の義務とは?
内容と具体的な対応方法
公開日:2024 / 6 / 21

企業における業務のデジタル化が進む中、それに即した法制度が整備されてきました。電子帳簿保存法による、電子保存の義務化もその一つです。
電子帳簿保存法では事務業務や管理業務の利便性を図るため、これまで改正を重ね、今では多くの書類の電子データでの保存が認められるようになっています。そして2022年1月施行の改正電子帳簿保存法には、電子取引データ保存の「義務化」が盛り込まれました。一定の要件のもと、2023年12月までの宥恕期間が設けられていましたが、2024年1月からは完全義務化となっています。
今回は電子保存に関する義務について、企業が知っておくべき情報をまとめました。
電子保存の義務とは
企業が保存すべき帳簿類については、電子帳簿保存法によって詳細が定められています。
電子帳簿保存法では電子データによる保存について以下の3つに区分しています。
- 電子帳簿等保存:電子的に作成した帳簿書類をデータのまま保存する
- スキャナー保存:紙で受領・作成した取引関係書類をスキャンしてデータ化し保存する
スキャナー保存について詳しくは、次の記事をご覧ください。
「電子帳簿保存法におけるスキャナー保存とは?そのポイントを解説」 - 電子取引データ保存:電子的に授受した取引関係書類のデータをデータのまま保存する
上記のうち1,2は任意ですが、3については2024年1月から完全義務化されているため、原則的にすべての企業で対応が求められます。
「電子取引」に該当するのは、契約書や領収書、請求書などを電子メールやクラウドサービスなどを利用して電子データでやりとりした場合です。関連書類を紙ではなくデータで受領している場合は、オリジナルの電子データの状態で保存しておく必要があります。
電子保存が義務化された背景
デジタル化が進む時代の流れにより、税務処理においてもIT技術の活用を求める声が拡大していきました。それに応じるため、従来紙での保存が義務付けられていた帳簿書類について電子データでの保存を容認する「電子帳簿保存法」が、1998年に創設されました。
社会全体でデジタル化が浸透していく中、それに合わせて電子帳簿保存法は改正が繰り替えされています。
最初の2005年の改正で電子取引における取引情報の電子データ保存はすでに義務付けられていましたが、書面(紙)による出力・保存も認められていました。今回の改正ではそれが廃止され、完全義務化となっています。
なお電子帳簿保存法の創設時に、すでに「電子データ等による保存を容認するための環境整備として、EDI取引(取引情報のやり取りを電子データの交換により行う取引)に係る電子データの保存を義務付けることが望ましい」との答申があり、今回の電子取引データ保存の完全義務化は、電子帳簿保存法創設からの規定路線とも言えます。
電子保存の義務に対応するため抑えておくべき法律と保存要件
電子取引データ保存は電子帳簿保存法で義務付けられており、保存に際しては守るべき保存要件があります。
電子帳簿保存法の概要と電子取引データ保存の概要、対象書類の例、電子取引データ保存の保存要件について順に紹介します。
- 電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律です。
電子帳簿保存法について詳しくは、「電子帳簿保存法をわかりやすく解説!必要な対応とは」をご覧ください。
- 電子取引データ保存の概要
先に紹介したように電子帳簿保存法の2022年の改定によって、電子取引における電子データによる保存が義務付けられました。
これはすべての事業者を対象に、電子取引でやり取りした請求書、領収書などの取引情報を含む電子データを、電子保存する義務を示します。
取引情報とは取引先・取引日・取引金額などの事項のことです。注文書や契約書、送り状、領収書、見積書などに通常記載される内容と考えればよいでしょう。
- 電子取引の対象書類の例
電子取引の対象となる書類の例としては、クラウドサービスによる電子請求、クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払いデータ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービス、EDIシステム、FAX機能を持つ複合機で受領した請求書データなどがあります。
電子取引データ保存の対象書類について詳しくは、「電子帳簿保存法の対象書類とは?一覧で紹介」をご覧ください。
- 電子取引データ保存の保存要件
電子取引データ保存の主な保存要件を紹介します。
<真実性の確保>
下記のいずれかの措置をとる必要があります。- タイムスタンプが付与された取引情報を受領する
- 取引情報の受領後、速やかにタイムスタンプを付与すると共に、保存の実行者または監視者に関する情報を確認できる環境を整える
- 訂正や削除を確認できるシステム、もしくは訂正や削除ができないシステムで取引情報の受領および保存を行う
- 訂正や削除の防止に関する事務処理規定を定め、それに沿った運用を行う
※ 電子取引データに関する事務処理規定のサンプルは国税庁でも用意されています。
<可視性の確保>
下記のすべてを満たす必要があります。- 保存場所に、パソコンやプログラム、ディスプレイ、プリンター並びにこれらの操作説明書を備え付け、画面および書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておく
- 電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
- 下記の条件で検索できるよう、検索機能を確保する必要があります。
- 「取引年月日」「取引先」「取引金額」の3項目
- 「取引年月日」または「取引金額」の範囲指定
- 複数の項目の組み合わせ
電子保存の義務に対応するためのステップ
電子保存の義務化に対応するためには、一般的に次のようなステップで進めます。
電子取引データ保存の対象となる保存が必要となる取引の把握を行う
取引情報をデータで授受している取引の洗い出しと、現在の業務フローの確認を実施します。対象となる情報を明確にし、不備のないよう現状からの移行対応を検討します。
保存方法に必要なシステムを導入する
システム導入に際しては、真実性の確保や検索機能の確保など、一定の要件を満たすものを選定します。
加えてシステム導入コスト、運用コスト、セキュリティ対策などを考慮する必要があります。ベンダーに導入・運用を依頼する際には、サポート体制についても確認しておくと安心です。
社内規定を整備し、従業員に周知徹底する
電子保存についての保存方法や保存期間、責任者、アクセス権限など、電子保存に関するルールを定めます。現場での混乱がないよう社内研修やセミナーを実施して、従業員に周知徹底することが大切です。
また、定期的に運用状況を監査し、円滑化を図ります。
必要書類を適切に保存する
適切な保存のために、保存対象となる書類の扱いをルールに従って処理することが重要です。タイムスタンプの付与や訂正・削除を確認できるか、もしくは訂正や削除ができない状態かなど、真実性の確保のための措置が正しく講じられていることを確認します。
また、アクセス権限の管理やセキュリティソフト導入、パスワードポリシーの策定といったセキュリティ強化も必要です。
税務調査時に電子データで帳簿書類を提出できる環境を整える
税務調査時に正当性を示せるよう、システムのそばに操作説明書があるか、取引年月日や取引先などで検索可能な状態かどうかを確認します。また、以下のような体制整備も必要でしょう。
- 電子データ閲覧ソフトを導入する。
- 税務署への電子データ提出方法を準備する。
- 税務調査時の対応を事前にシミュレーションしておく。
電子取引データ保存する際に知っておきたい対応については、次の記事も参考にしてください。
電子帳簿保存法に対応し請求書を電子データ保存する際知っておくべき基礎知識
電子保存の義務化に対応しながら今後に備えよう
2022年の電子帳簿保存法改正から2年の宥恕期間を経て、電子取引に関する電子保存が完全義務化されました。基本的にはすべての事業者が対象となります。今後はさらに電子保存の範囲が拡大し、いずれはすべての保存義務のある情報が対象になるでしょう。ペーパーレス化が国によって推奨される動きが加速する中で、企業では蓄積する情報のデータ化に取り組む必要があります。
WisOCRは手書きも活字もあらゆる書類を高精度にデータ化するAI-OCRソリューションです。
例えば企業内に蓄積した手書きの帳票類を迅速に大量処理する際などに、大きく貢献します。独自の「ハイブリッド型AI-OCRエンジン」により高い認識精度を実現し、初めての方にもわかりやすい操作性に加え、業務現場で役立つ多彩な機能を搭載しています。
電子保存の推進をご検討の際には、ぜひご活用ください。
関連記事
パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社では、注文書や請求書などの入力や転記作業に対応した「WisOCR for 注文書・請求書」と、申込書や作業報告書・検査表などのあらゆる紙帳票の入力や転記作業に対応した「WisOCR」という2つのAI-OCR製品をご用意しております。AI-OCRの導入を検討されている方は、ぜひ一度お問い合わせください。